
この記事を監修いただいた専門家
保健師 シホ
10年以上にわたり自治体保健師として感染症や母子保健などの業務に従事し、多くの住民に寄り添い支援を行う。他にも、病院看護師としての臨床経験や学校保健師としての業務経験など、幅広く公衆衛生に従事する経験を持つ。現在、一人娘を育てながら、ICTを使ってより多くの人々の健康支援に寄与できるよう、育児コラムの編集・監修などにも活動を広げている。趣味は映画鑑賞。
この記事を監修いただいた専門家
管理栄養士 隅弘子
(ひろ子先生)
10年以上にわたり自治体保健師として感染症や母子保健などの業務に従事し、多くの住民に寄り添い支援を行う。他にも、病院看護師としての臨床経験や学校保健師としての業務経験など、幅広く公衆衛生に従事する経験を持つ。現在、一人娘を育てながら、ICTを使ってより多くの人々の健康支援に寄与できるよう、育児コラムの編集・監修などにも活動を広げている。趣味は映画鑑賞。
マンガ「療育」






























療育とは
療育とは、困りごとを抱える子どもが生活しやすくなる、発達につながる支援のことです。将来的に社会において自立した生活が送れるように、子どもの特性に合わせて支援を行っていきます。1948年に東京大学名誉教授の高木憲次氏によって提唱された「医療」と「教育」をバランスを保ちながらすすめることが大切だという概念が語源になっています

療育を受けるメリット
子どもに発達の心配があり療育をすすめられたけれど、「うちの子は本当に療育が必要?」「早く受けた方がいいの?」と迷われる方もいらっしゃるでしょう。
療育を受けると次のようなメリットがあります。
①家庭での育児がスムーズになる
子どもの困りごとに対するサポート方法を知ることで、子ども自身も生活がしやすくなったり、保護者としても育児がスムーズになります。

②発達の土台を作り次の成長につなげられる
言葉・運動・社会性・感情コントロールなどを専門的に支援してもらえるため、子どものペースで土台を最大限作り、次の成長につながりやすくなります。

③同じような悩みをもつママ・パパと交流できる
まわりの子どもと比べ不安になったり、孤独を感じている方もいるのではないでしょうか。同じような悩みをもつママ・パパと情報共有できたり、「悩んでいるのは自分ひとりではないんだ」と気持ちが楽になることもあるようです。

④二次障がいを防ぐことができる
子どもが周囲に理解されず困った状態が続くと、自己肯定感の低下など二次障がいにつながってしまうこともあります。困りごとの原因に障がいがある場合は、その特性を踏まえたサポートが効果があります。子どもの特性を知って、環境や人間関係によるストレスを予防・軽減してあげましょう。

「療育」を受けたほうがいいか悩んでいる場合は
かかりつけの小児科医や、お住まいの市区町村の保健センター、児童相談所、療育を受けられる施設などに相談してみましょう。一人で抱え込まずに、まずは相談してみることが大切です。 また、療育には、いつから始めるべきという明確な基準はありません。保護者の方が心配や必要性を感じたら、早めに相談してみましょう。
療育を受けられるのはどんな施設?
療育センター
療育センターとは、困りごとを抱える子どもや障がいがある子どもが、医療、教育、治療、リハビリテーションなどの支援を受けられる施設です。 提供する支援内容に応じて、医師や看護師、保育士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、臨床心理士、心療発達心理士などのさまざまな専門職のスタッフが在籍しており、医療サービスと福祉サービスを合わせて受けることができます。
児童発達支援センター
児童発達支援センターは、児童福祉法に規定された施設です。発達に支援が必要な就学前の子どもを対象に、日常生活の基本動作を身に付けたり、集団生活に適応できるよう療育を行ったりします。 また、保護者が施設に発達の相談をすることにより、子どもの健全な発育の促進及び子育てに関する不安の軽減を図ることを目的としています。
その他の施設
民間の児童発達支援事業所、放課後デイサービス(就学児)、専門の医療機関などで療育を受けることができます。
療育の専門職のスタッフ
| 作業療法士(OT) | 食事や着替え、遊びなどを通して、「手の使い方」や「体の動かし方」を練習し、生活のしやすさをサポートします。 |
|---|---|
| 理学療法士(PT) | 立つ・歩く・走るといった動きを中心に、体のバランスや筋力を育て、動きやすい体づくりをお手伝いします。 |
| 言語聴覚士(ST) | ことばの理解や発音、コミュニケーションの力を育てます。また、食べる・飲み込む練習を行うこともあります。 |
| 臨床心理士 | 気持ちや行動の面からお子さんをサポートします。カウンセリングや心理検査を通して、心の発達を見守ります。 |
| 心療発達心理士 | 発達や心の状態を総合的にみて、お子さんやご家族が安心して成長できるように支援します。 |
園に通いながら利用できる
保育園や幼稚園に通い始めてから、集団生活の中で子どもの様子をみて「何か困っているかもしれない」と園の先生や保護者が気づき、療育の検討を始めるということもあると思います。これから療育センターや児童発達支援施設を利用しようか…と考えている場合でも、保育園や幼稚園をやめる必要はありません。
保育園や幼稚園と療育をうまく組み合わせ、集団生活の経験を維持しながら、発達をよりサポートすることができます。
療育での内容を園の先生に共有することで、日常生活の中でサポートが受けやすくなったり、その内容を園でも実践してもらったりすると、より効果的な学びにつながります。
また、園で困っていることを療育で重点的にフォローしてもらうこともできるので相乗効果が生まれます。
直接、施設のスタッフが園を訪問(保育所等訪問支援)をする場合もあります。

療育と園で連携した例


利用の流れ
利用するまでの流れ
①発達の相談をする
乳幼児健診、保育園(幼稚園)、保健センターなどで発達の心配事や専門医の受診が必要かなどを相談する。

②専門医を受診する
専門医を受診し、医師から「療育が必要」という内容の診断書や意見書をもらう。(専門家の意見)

③利用する療育施設を決め、申し込む
施設の見学や体験をして利用する施設を決め、申し込む。
施設で障がい児支援利用計画案を作成してもらう。
※病院に医療サービスや福祉サービスが併設されているところもあり、施設を指定される場合もある。

④受給者証の利用申請をする
お住まいの市区町村の福祉課で通所受給者証の利用申請をする。
※通所受給者証があると、福祉サービスの利用料を公費で負担してもらえる。(世帯収入等によって自己負担額が決まる)

申請時の持ち物
支給申請書(市区町村窓口もしくはダウンロード)、障がい児支援利用計画案、医師の診断書や意見書(持っている場合は障がい者手帳)、マイナンバーカード、印鑑など
※市区町村によって違うので、事前に確認しましょう。
施設の利用開始
①アセスメント
利用をはじめるにあたって、保護者と施設のスタッフで普段の子どもの様子について面談をしたり、子どもの行動の観察をしたりなどのアセスメント(査定、評価)が行われます。
②支援計画にもとづいた支援プログラムを受ける
子どもの特性にあわせて、施設のスタッフが個別の支援計画を作成し、その計画に沿って個別や集団でサポートを進めていきます。
支援プログラムの例
運動療法

身体を動かして運動能力や体力を向上
言語療法

遊びを通してことばの発達を促進
SST
ソーシャルスキルトレーニング

人との関わり方、社会生活に必要なスキルを学ぶ
音楽療法

音楽を聴いたり演奏したりすることで、感情の調整や集中力が向上
ABA
応用行動分析学

子どもが問題となる行動を起こすのはどんな時か分析
作業療法

日常生活を送るうえで必要な機能の回復
遊戯療法

遊びによって心の中を外に出し心を理解する
感覚統合療法

さまざまな感覚を適切に対処できるようにする
TEACCH
自閉症スペクトラム症のある人々とその家族を対象とした、アメリカで生まれた包括的な支援プログラム

自閉症による発達の凸凹を社会に順応できるようにする
支援内容は施設によって異なりますので、詳細は問い合わせましょう。
利用料金はいくらかかる?どんな助成がある?
療育の利用には料金がかかりますが、助成を受けられる場合が多いです。 医療サービスを利用するか、福祉サービスを利用するかにより助成の内容が違います。
医療サービスは健康保険や乳幼児医療費助成が使える
例)リハビリや医師による診察・検査など
健康保険・乳幼児医療費助成受給者証・小児慢性特定疾病受給者証が使えるので、自己負担額はかからないことが多いです。(市区町村による)
福祉サービスは「通所受給者証」が使える
例)児童発達支援(未就学児)・放課後等デイサービス(就学児)など
お住まいの市区町村が発行する「通所受給者証」があれば、自己負担が1割で利用できます。自己負担金は、所得に応じて月額の上限があります。
| 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 (前年度の年間所得890万円まで) | 通所・短期入所施設 | 4,600円 |
| 入所施設 | 9,300円 | |
| 市町村民税課税世帯 (前年度の年間所得890万円以上) | 37,200円 | |
| ※2025年8月現在 | ||
3歳から5歳は幼保無償化の対象
- 幼児教育・保育の無償化
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間は無償 - 多子軽減措置
兄または姉がおり、一定の要件を満たす世帯に対し、第2子以降の当該児童に係る利用料を軽減
※ほかにも市区町村の独自の助成がある場合もあります。市区町村の福祉窓口で確認しましょう。
どの施設に通えばいいのか悩んだときは?
- 通いやすいか(自宅から近い、保育園から施設に送迎があるなど)
- 受けたい支援内容が合っているか
- 利用できる回数はどれくらいか
- 見学したときの子どもの反応
- ママ、パパがスタッフに相談しやすいか
などをポイントに決めるとよいでしょう。
体験談

「一緒にみていてくれているんだ」と感じられ心の負担が減りました
歩くのも発語も成長が遅めだったのですが、2番目の子どもということもあり、「焦らなくても大丈夫だろう」とのんきに構えていました。2歳半頃、健診で「ことばの発達が遅い」という指摘を受け、療育への相談を勧められました。自宅の近くに小児発達科のある病院内に療育施設があったので、言語療法を月に2回のペースで受け始めました。音楽や絵カードなどを使いながら楽しく発声したり、ストローを吹くゲームなどをアドバイスいただき、保育園でも取り入れてもらいました。
それまで家庭では「何をしたらいいのか分からない」状態だったのが、「こうしたらいいよ」という方法を知ることができて、子どもが困っている時の対応に迷わなくなりました。
仕事を休んでの送迎は大変でもありましたが、何よりも療育のスタッフ、保育園の先生、地域の保健師さんなどが「一緒にみていてくれているんだ」と感じられ心の負担が減りました。

子どもが成長している姿がハッキリ分かり、親の心の支えになりました
首がなかなかすわる気配がなく乳児健診で相談し、生後10か月頃から保健センターで理学療法を受けることに。その後、小児発達科のある病院で理学療法、言語療法、作業療法を受けました。
3歳頃から児童発達支援に通いたいと思い、保健師さんから役所の担当課につないでもらい施設の見学をしました。子どもにピッタリの施設(理学療法、言語療法、作業療法がそろっている)を見つけることができました。施設によって内容や方針が違うので見学してよかったです。
保健師さんからは「小学校入学まで、成長を見守りたい」と言っていただき、半年に1回くらい保健センターにも通いました。
また同時に保育園にも通うようになりました。児童発達支援施設が保育園から送迎をしてくれるところだったので、とても便利でした。保育園でも、支援計画を考えてくれて、子どもの成長に合わせて参加できることを増やしていったり、目標を立てながら成長に寄り添ってくれ、学校の集団生活に慣れていくための良い経験になりました。
療育は、子どもの成長してほしいところにピントを合わせて支援してくれるので、療育施設と保育園を併用して本当に良かったと感じています。ゆっくりですが子どもが成長している姿がハッキリ分かり、親の心の支えになりました。
まとめ
子どもの成長や発達に不安があったり、障がいがあるときは、療育センターや児童発達支援センターなどで支援を受けることができます。専門のスタッフと一緒にお子さんの心配なことや苦手なことのサポート方法をみつけていきましょう。お子さんの好きなこと、得意なことを増やして、親子ともに生活しやすくなるといいですね。

- 「療育園で」
- ずっとついていきます、先生~!

- 「ママと呼ばれる日まで」
- 違うんかい!(笑)
-
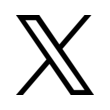 Post
Post -
 シェア
シェア -
 LINEで送る
LINEで送る




他のマンガにもコメントが届いています。
-
![「粋な計らい」]()
1
![さん]() 初々しく さん
初々しく さん
-
![つわりはいつから始まりピークはいつまで?症状と対処法について]()
1
![さん]() みりん さん
みりん さん
-
![「いつでも抱っこ!」]()
1
![さん]() あいうえお さん
あいうえお さん
みんなのコメントをもっとみるわかる~
がんばって!おうえんしてます!
私の子どももそんな時期あったなぁ~。 だっこできるのは今のうちだからなるべくしてあげたいよね。